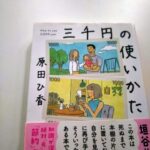最低賃金(時給)の全国加重平均額が1118円に
2025年度の最低賃金(時給)が、全国加重平均で63円(6.0%)引き上げられて1118円に決定された。これは全国平均なので、最も高い東京都は1163円から1226円になり、最も低い秋田県は951円から1015円となる。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6547975
最低賃金については、政府は「20年代に全国平均1500円」との目標を掲げているので、あと5年以内に1500円の達成は厳しいかも知れないが、最低賃金の増額傾向はしばらく続くのではないだろうか?
最低賃金の増額の問題点
労働者サイドから見ると、最低賃金の増額は結構な話と思えるかも知れないが、必ずしもそうとは限らない。結局、労働コストの上昇は、財やサービスの価格に転嫁されてしまうからだ。企業側が賃金の増額分を吞んでくれるはずもなく、その分は結局、消費者の負担となる。
名目上の賃金は増えても、結局、インフレになって、実質的に生活に余裕ができるわけではないのである。
この点、労働者以上に辛い立場にあるのは、年金生活者である。年金もインフレにスライドするが、到底、インフレ率には追い付かない。
また、インフレとは別の問題として、特に地方の体力の無い中小企業が、この賃上げ基調についていけるかという点も気になるところである。そうなると、採用を抑制して仕事が減るとか、或いは、体力のある企業に労働力を持っていかれて、ますます都市部への流入と地方の過疎化が進んでしまうという弊害も考えられる。
定年後の年金生活を見据えた対応策
最低賃金の引き上げについては、与党も野党も賛成だという。そうなると、この労働コストの上昇基調は継続すると見た方がいいだろう。そうなると、インフレの継続も考慮しておく必要がある。
インフレ対応については、文句を言ったところで誰も助けてくれないので、自分で出来ることはやっておく必要がある。
私も2023年までは金融資産のほぼ全てが預貯金と個人向け国債という状況であったが、インフレの進展とコロナ以降の株高を見て、さすがにこのままではマズいと考えるようになり、半年以上の勉強期間を経て、2024年の夏から積立投資、外債・日本株投資(いずれも投資信託)を始めることとした。
私もそれまでは、サラリーマンが積立投資をしたところで大した効果はないだろうと思っていたのだが、毎月5万円を想定利回り5%で10年間積み立てると、776万円になる。毎月7万円を想定利回り5%で10年間積み立てると1,087万円になる。これは決して小さな金額ではないし、サラリーマンにはボーナスがあるので、家計の見直しを行って頑張れば実行可能だろう。
とは言え、焦って退職金を運用に回さない方がいい
ただ、積立投資は長期間やればやるほど効いてくるので、始めるなら早い方がいい。
しかし、現役時代に運用を一切やらず、定年のタイミングで焦って退職金を元本保証でない金融商品で運用するのは避けた方がいい。これは、多くの経済評論家やFP(ファイナンシャル・プランナー)が言っていることだ。
運用に関する知識や経験がほとんど無い状態で、金融機関にボーナス金利付きの定期預金と抱き合わせで、変な投資信託とかを買わされるとロクなことは無いだろう。さらに、個別株の売買とか、FXとか仮想通貨にまで手を出すようになると目も当てられない。
退職金は、預貯金と個人向け国債(変動10年)あたりの元本確保のものにキープしておくのが無難だろう。
積立投資をするのであれば、再雇用になると収入が大幅減になるので十分な原資が無いかも知れないが、月に1万円とか2万円といった少額から始めていくのがいいと思う。
若い時と違って、正社員としての定年を迎えてしまうと、取り返すことが非常に厳しくなってしまう。
最後の手段は、働いて収入を得ること?
現役の時に積立投資はやって来なかったし、退職金を運用に回すなと言われると、どうやってインフレに対応するのか?
これについては、「節約」を頑張るか、働いて収入を得ることしか、思い浮かばない。「節約」には限度があるので、そこで行き詰ると、最後の手段はアルバイトでも何でもいいので働いて収入を得るしかない。
実際、インフレが原因かどうかはわからないが、高齢者の就業率は年々高まって来ているようだ。60~64歳では約75%、65~69歳は50%以上が働いている。更に、結構驚きだったのが、70~74歳でも1/3以上が働いている。https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/gaiyou.pdf
ただ、アルバイトだからと言って、60歳を過ぎると、簡単に好きな仕事を選べるわけではない。例えば、人手不足が深刻だと言われる飲食店のバイトも、60歳以上は敬遠されがちで、「土日勤務可」と言わないと難しいという話を聞いたことがある。結局、高齢者でもありつける仕事は、警備・清掃・介護、ということになるが、長年ホワイトカラーをやっていたサラリーマンにとっては慣れない仕事である。そう考えると、「賃金大幅減」「仕事のやりがいに欠ける」といった不満の多い再雇用でも、中途半端にやりたくないバイトをやるくらいなら65歳まで目一杯働いた方がいいという考えもある。
元々は最低賃金⇒インフレ⇒年金の目減り、ということであったが、その対策としては、積立投資、最後の手段は働くことと、話が逸れた。昔は、60歳で定年になると働かないのが普通であったように記憶しているが、今では65歳まで働くのが普通になってしまった。将来は、70歳まで働くのが普通になってしまうのだろうか?