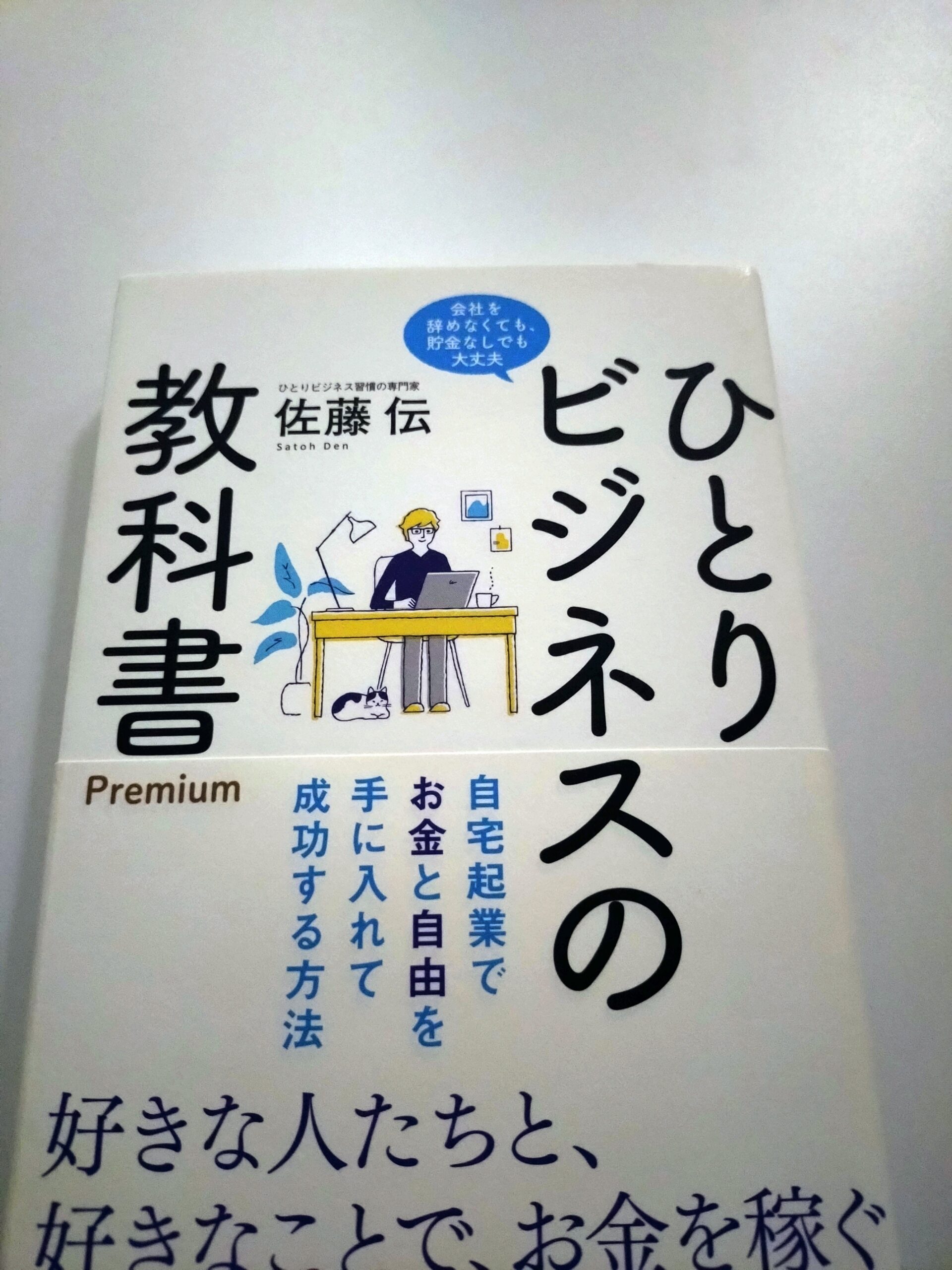定年後の「ひとり起業」に興味はあるが、どうすればいいかわからない
私は50代の定年準備中のサラリーマンだが、正社員としての定年後には、再雇用やアルバイト的な働き方ではなく、「ひとり起業」を目指している。「起業」と言っても大げさなものではなく、リスクは取りたくないので、お金がかからないネットビジネスを考えている。
私の様に、定年後は「ひとり起業」をやりたいと考えるサラリーマンはそれなりにいるのではないだろうか?その理由は、「再雇用」が面白くないからである。再雇用になると、年俸半分は当たり前、ひどいと1/3以下に減らされ、肩書まで剥奪され、モチベーションが激減するからである。
しかし、「ひとり起業」に漠然とした関心があっても、いったい何から始めればいいのか全く見当もつかないサラリーマンは少なくないだろう。サラリーマンは組織の中で働くので、集客から売り物まで全て、ひとりで考えて実行するという経験はしていないからだ。
また、周りに、こういったことを教えてくれる人も普通はいないだろう。
そこで、参考になるのが、「ひとりビジネスの教科書」(佐藤伝著)である。
本書は、サラリーマンや主婦が「ひとり起業」を始める際のバイブルであり、名著とされているものである。そこで、今回は、私自身の備忘録も兼ねて、そのポイントを紹介したい。
https://hon.gakken.jp/book/1340680500
本書の概要
本書は7章構成になっており、基本的に時系列に沿って「ひとりビジネス」の企画から実行までを解説してくれている。
私が思うに、本書で特にキーとなるのは、第1章と第2章である。
ビジネスは、まずに「売りもの」があって、それを顧客に販売することによって成立する。本書の第1章と第2章は、このうち「売りもの」について説明している。
売りものが無いとひとりビジネスは始まらないので、この最初の二つの章をキッチリと理解し、考えながら読み進めることが重要である。
自分の「売りもの」の見つけ方
「テーマ」を決めることが最初
「売りもの」を見つけるには、まず「テーマ」を決めなければならない。
ここが非常に重要なのだが、例えば、「テーマはどうしますか?」と聞かれて、「コーチングです」と答えるのでは不十分である。
この例だと、「コーチング」だけでは不十分で、例えば、「子育てに悩む母親」に対して、「育児の悩みの解決法を」、「(対面又はZOOMで)個別的な対面コンサルティングによって解決する」、までが必要ということである。
要するに、「誰に」「何を」「どのように」、というのがセットで必要になるのである。
「AからBへ変わる方程式」:ソリューションの提供になっているか?
そして、本書は先ほどのテーマの是非について、非常に良いテストの方法を紹介してくれている。それは、テーマは顧客に対して、ソリューションを提供できるか、自分のコンサルティングの前後で顧客は変わることができるかを考えよということである。
上の例だと、たとえば、「両親が遠方で、旦那は育児に非協力的で、日々精神的・肉体的に疲弊している母親」が、自分のコンサルティングによって、「旦那に協力してもらったり、ママ友同士のコミュニケーションで鼓舞され、精神的余裕や自信が持てた」という状態に持っていけるのかということである。
ここの具体的なイメージを持てるまで、「テーマ」を練る必要がある。
自分が具体的に悩んで、それを解決できた経験やスキルがあると、「売りもの」にすることが可能である
上の話を聞くと、思っていた以上に「売りもの」を考えることは難しいと思うかも知れないが、反対に、他の人が持つような悩みを解決できた経験があれば、特別な技能や資格が無くても、「ひとりビジネス」における「売りもの」は可能ということである。
サラリーマンの場合であれば、例えば、「苦手な上司と上手く良好な関係にする工夫」とか、「パフォーマンスの低い部下の働きぶりを改善するノウハウ」、或いは、「英語力に自信が無いのに、初めて海外赴任する場合の対処法」等、長年サラリーマンをやっていると、いろいろな切り口があるのではないだろうか?
更に、「売りもの」を練り込んでいく
本書では、更に「売りもの」を磨いて行く方法について解説している。
本書の例では、フィギュア作りが得意でネット販売している人の例が紹介されている。
この人はフィギュア作りが上手く、そのフィギュアの出来栄え自体は良いのだが、なかなか売れなかった。
しかし、ちょっと工夫をすると状況は一変する。
「ランドセルを背負った子供」のフィギュアを、小学校の入学のお祝い用のグッズとして販売すると非常に売れるようになったそうである。
「何を」「誰に」「どのように」に加え、「何時(どういったシチュエーション)」という切り口を加えると、一気に変わる可能性があるということである。
ある意味、ひとりビジネスと言うのは「絞り込み」のビジネスなので、どんどん絞り込んで考えて行くと、チャンスは生じるものなのである。
意外に重要なのが、「ミッション・ヴァリュー」
大企業の「ミッション・ヴァリュー」というのは、いかにも綺麗事だし、個々の従業員まで浸透していないため、実際上の重要性はあまり高く無いかも知れない。
しかし、「ひとりビジネス」の場合は、意外と軽視できないのである。
著者は、「コア・メッセージ」という言い方をしているが、本書では著者がコンサルをした出版熟のケースが紹介されている。
著者が出版熟の人達に「コア・メッセージは何ですか?」と質問したところ、特に回答は得られなかった。そこで、新に「コア・メッセージ」を考え、「本で世界を変える!」とすると、それを機に一気に売上が増えていったというケースである。
「ひとりビジネス」の場合は、大企業と異なり、その人の個性や人柄が「売りもの」の価値に直結するので、明確で良いコア・メッセージがあると、「何を」「誰に」「どのように」にを通じて、それが顧客に対してより明確に通じるからだという。
「コア・メッセージ」の重要性については、著者の教え子の章末の「事例ファイル01」でも取り上げられている。
この方は、自分自身が「アダルトチルドレン」の傾向があることに長年悩み続け、セラピー、心理学、脳科学、コーチング、占いなどコツコツ時間を掛けて学んできた成果を、他の同種の悩みがある人にコーチングをするというビジネスを展開している。
この方は、本気で「本当の自分を生きることで、悩んでいる人を『何となくイイ気分で』いられるようにすること」いうコア・メッセージを持っているので、それが顧客にもキッチリ伝わっているのではないかと思われる。
ワクワク感のテスト
本書の第1章・第2章を読むと、いかに具体的で、本気度の高い、顧客の問題解決につながる「売りもの」を作ることが重要かということが理解できるのだが、もう1つ大事なことは、自分自身が楽しんでやれるということである。
これを著者は「ワクワク感」と表現しているが、自分自身が「ワクワク感」を持てないと、結局続かないし、そもそも、自分が好きな事をやるために「ひとりビジネス」を始めるわけなので、この点も非常に重要である。
「好きなこと」「得意なこと」でも、それが顧客のソリューション(悩み解決)につながらないとビジネスにならずに、単なる、趣味・特技で終わってしまう。
他方、特定の人にとって非常に強力で魅力的なソリューションを「売りもの」にしようとしても、自分が興味を持てなかったり、得意でなければビジネスは続かない。
この、「好き・得意」と「顧客のソリューション」の2つがビジネスに必要なところが難しいところだが、この2つをクリアできると、かなり成功に近づけるのではないだろうか?
まずはキッチリと「売りもの」を用意できれば、あとは、価格や販売戦略におけるテクニックで何とかなる?
本書の3章以降では、「販売」や「価格」戦略についての手順やコツが書かれている。
ブログ、SNSを使って、如何に集客するか、価格設定や商品ラインナップはどうするか、ネットとリアルを上手く使い分けるといった内容である。
ただ、やはり大事なのは「売りもの」である。
反対に、良い売りものがあれば、あとは粘り強く、ブログやSNSで発信力を高めて行くかである。この集客については、「量」(記事数や発信頻度)で、頑張れば何とかなる世界である。
他方、「売りもの」については「質」「センス」が必要となる。
ここが、定年後の「ひとり起業」の成否のカギとなりそうであるので、定年前でも「売りもの」について、じっくり検討してみればいいだろう。また、集客手段としてのアメブロとかThreadsとかも早い段階で試しておくことが、定年後「ひとり起業」の準備となる。これらは、特に費用も掛からないので、まずは始めてみて、やりながら上達を目指すことをお勧めしたい。